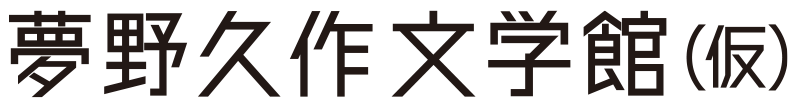星行
「私、駆け落ちすんの。これ誰にも秘密ね」高校に上がったのを機に全く話さなくなった幼馴染からの言葉に私は耳を疑った。「久しぶりに一緒帰らない?」と誘われ緊張していた脳がまるでスパーンと弾けた気分だ。
「今晩ね、あそこの河川敷の橋の下で会おうって彼と約束してるんだ。彼と二人でこの町から出て生きていくの」
確か、彼女の家庭は厳しかったはずだ。趣味から遊ぶ相手まで全てに口出す親で、当時幼かった私の目から見ても異様だった。しかし、うちの町は時代遅れな田舎だからそういうのに目を瞑るなんてことも珍しくなかった。
「…そんな相手がいるなんて知らなかった」
「そりゃあ、誰にもバレないように会ってたからね。イロハだけじゃなくて誰も知らないと思うよ。メールや文通もしてないから証拠もないし!」
「へえ。その彼って誰なの?」
「それはイロハにも秘密!」
「…そっか」
やるなら徹底的に、頭にいい彼女らしい。強かで同性の私から見ても愛らしい幼馴染。そんな彼女が選んだ相手だ。言わずもがな彼女に引けを取らない相応しい相手なのだろう。幸せの絶頂だと言わんばかりの顔をする幼馴染に釣られて私もつい頬を緩めてしまう。
「ねえ、なんで私に話したの?」
「誰かに本当の私を話しておきたかったの。突然私がいなくなっても、犯罪に加担してるだとか家出した親不孝娘だとか思わずに本当の理由を知ってる人がいてほしかったから」
確かに、いまどき駆け落ちする人なんていない。ましてやこんな田舎町、幼馴染が姿を消せば誰もが彼女を悪く言うに違いない。それを見越している彼女は、やはり、頭がいい。
「ほら、イロハは口が堅いでしょ?」
「よく言われる」
分かれ道、ここで幼馴染と別れる。手を振って離れる間際、学校の先生にもどちらの親にも言ったら駄目だと念を押された。
三日後、河川敷の橋の下で幼馴染の死体が見つかった。彼女の死体の周りには他の死体も誰かがいた形跡もなく、ただ必需品がギッチリ詰まったトランクだけがあったという。ああ、あの頭のいい幼馴染でも盲目になることがあるんだなあ、なんて。頭の悪い私にはそういう感想しか浮かばなかった。